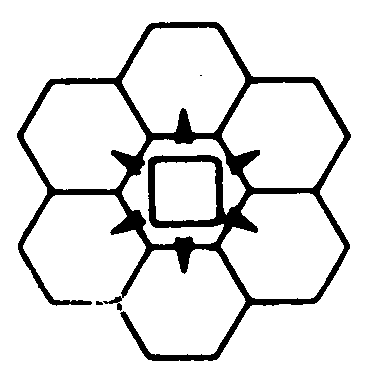
- ZOC展開の可否:地形効果表(TEC)に基づき、ZOCを展開できるかをユニット個別に判断する。自身のいるヘクスを含めて、侵入可能な地形(BT)にのみZOCを展開できる。凍結していない海や河川がある場合、それらを越えてZOCを展開することはできない。
ex. 機械化部隊及び自動車化部隊は、森林や山岳などの複数のBTに対して侵入不可能であり、森林や山岳などの複数の侵入不可能BTに対してZOCを展開できない。森林や山岳などの侵入不可能BTヘクスであっても、隣接ヘクス内に道路や鉄道がある場合、道路や鉄道を利用した移動(Mv.mode)では侵入可能となる。その隣接する道路や鉄道に対してのみZOCを展開できることに注意して欲しい。 - ZOCの展開:自身のいるヘクス及び各隣接ヘクス個別に、ZOC展開可能な部隊のスタック・ポイント:Stack Point(StP)を合計し、『ZOC展開表』と照合の上でそれぞれのヘクスに対するZOCの展開状況を判断する。
ex. 機械化部隊及び自動車化部隊は、森林や山岳などの複数のBTに対して侵入不可能であり、ZOCを展開できないことに注意すること。しかし、道路や鉄道で繋がっている状態であれば道路や鉄道を移動する「道路/鉄道移動モードMv.mode」での侵入可能である。そのため、 「Mv.mode」であれば、道路上にのみZOCを展開できることにも注意すること。加えて、それらが歩兵部隊とスタックしている場合、歩兵部隊のみが森林や山岳などにもZOCを展開可能ではあるが、その歩兵部隊が「展開モード」と「Mv.mode」のどちらなのかでZOCを展開が可能かどうかが決定される。移動終了時に展開モードとすることも可能であるが、「Mv.mode」で終了した時には、「対応アクション」による「近接展開攻撃」を受ける可能性は常にある。「戦闘状況決定表」を参照すること。 - ZOCの強度:『ZOC展開表』は、「+xZOC」という形式で「侵入/離脱に必要となる追加移動力」を示すことによって、ZOCの強度を示している。
- ZOC展開の3段階:中心部から中心部から「自身が存在するヘクス内の拠点に対するZOC(Defence Point ZOC:DPZOC)」・「自身が存在するヘクス内の拠点周辺部のBTに対するZOC(Close Deployment ZOC:CDZOC)」・「隣接ヘクス内BTに対するZOC(Adjust Deployment ZOC:ADZOC)」の3段階が存在する。
- 複数ヘクスによる影響:あるヘクスに対して複数の隣接ヘクスからZOCが展開されていることとなろう。この時、「最大値となるxZOC」を適用する。加算されることはない。
- ZOCの離脱と侵入:同一ヘクス内でも各段階のZOCが展開されている。その時、侵入及び離脱について「最大値となるxZOC」を適用する。加算することはない。
